勉強ができるだけではこれからの時代に通用しない?
わが子の未来を思うからこそ、小学校に上がったらしっかり勉強してほしいと思うもの。
しかも変化の早いこの時代、なんとか振り落とされずについていけるだけの力をつけてほしいと思いますよね。
お皿洗いながら、洗濯しながら聞ける動画バージョンはこちら🎵🎵
子どもたちに求められる力は、私たちが子どもだった頃とは大きく異なっています。
たとえば私たちは
- 漢字をたくさん覚える!
- 社会系は丸暗記!
- 英語も単語と文法を覚えればOK!
- 数学だって解法を暗記すれば素早くとける!
- 理科系の科目も暗記がなければ始まらない!
みたいな感じじゃありませんでした?😂😂
とにかく覚える!ひたすら覚える!私の場合、数学の解法なんか仕組みもわからず意味も分からずただ覚えてましたよ!(笑)
しかし、こうして表面上だけで覚えた知識は、社会に出ると途端に使う機会がなくなります。

sine、cosine、tangentのグラフってどう書くんだっけ…?
molってどんな意味だったっけ…?
英語の大過去の構文ってなんだっけ?
そう、学校では暗記をさせるだけで、その裏にある仕組みや理由までは触れる時間がとれないのです。
こうして「答えは誰かが持ってるんだから、わざわざ自分で考える必要はない。誰かの答えを覚えればいいだけ」という思考の人間ができあがります。
これが「指示待ち人間」ですね😱😱
思考力を伸ばすはずの数学でさえ暗記になってしまっているんだからもったいない💦💦
確かに、これまでの社会ではいろいろなものを「暗記」できれば通用しました。
仕事のマニュアルを覚え、営業のマニュアルを覚え、クレーム処理のマニュアルを覚え…その積み重ねで仕事をしていくことができていました。
しかし、数学の解法も、英単語も英文法も、ただ単に暗記しているのではすぐに忘れてしまいましたよね?😅
仕事も同じで、何も考えずにただ覚えているだけでは、今までにない新たな問題にぶつかったときに動けなくなってしまうのです。
せっかく若い時間を学校で費やすのですから、「どうしてこの解法でこの問題が解けるんだろう?」と自ら疑問を持ち、多角的に考える訓練を繰り返さなくてはもったいないですよね。
暗記しかできない人材は、今後の社会でなかなか求められなくなっていきます。
だからといって、深く考える力をじっくり育てる余裕は学校にはありません。
だからこそ、おうちでの親の力が重大になってくるんです。
お皿洗いながら、洗濯しながら聞ける動画バージョンはこちら🎵🎵
会話の中で子どもが考える「隙」を与えよう

考える力を伸ばすためにおうちでできることがあるの?

誰もが毎日やっていることで、子どもの考える力を伸ばすことができますよ
数多くの未知な問題に直面しているこのご時世だからこそ、自分で考え、決断し、行動することができる人間が求められています。
今回は思考力に絞って、おうちでできることを紹介しますね🌼
それは、
会話の中で子どもが考える「隙」を作ること
なんです。
親はどうしても「早く着替えて」「ハンカチ持った?」「水たまりで遊んじゃダメ!」など、先回りして発言しがちですよね💦💦
子どもが失敗しないように、子どものためを思って言っていることなんですが、この先回りの声掛けが結果的に子どもが考える「隙」を奪ってしまっているんです😖
まずは「正解の行動を今すぐにとってもらって、失敗を回避させよう」と考えるよりも「どうしてこうしないといけないんだろう?」と疑問を持てるようにサポートすることが大切。
考える力を伸ばすには、3つのステップが必要です。
- 疑問を持つこと
- 解決策を探すこと
- 自分の言葉で表すこと
親としては「汚れるから水たまりで遊ばないで」とすぐに答えを渡したくなりますが、考える力を伸ばしたいのであれば「どうして水たまりで遊んじゃいけないんだと思う?」と切り口を変え、子どもに疑問を持ってもらうことも大切ですよ。
「水たまりさんが痛いから?」のように少し変な答えが返ってきても、それはその子の答えなので受け入れてあげてください😊
逆に、答えが出なくてもそれは1つの答えなのでOKだと思いますよ。
「水たまりさん痛いかもね。どうしたらいいかな?」と次は解決策を探してみましょう🎵🎵
遊ぶのはやめる?水が跳ねないように静かに遊ぶ?裸足なら痛くないかもしれないから靴を脱いで遊ぶ?

裸足で遊ぶの楽しそうー!

こういう答えが来ても、まずは「いいアイディアだね!」と受け入れてあげたいですね
子どもの意見をなんでも採用するというわけではないので、「裸足で遊ぶ」のように親が困ってしまうような答えが出てきたら「おもしろいね!でも足が汚れるとお母さん悲しいから、別な方法を考えてみようか」と提案しても良いと思いますよ。
そこでまた考えがまた深まっていきますからね👌
まずは疑問を持つこと、どうしたらいいか考えること、たどたどしくても自分の言葉で表現することをサポートしてあげたいもの。
考えることができるようになれば、自分で納得した答えが出せるようになるので、周りの意見に流されることがなくなります。
みんなが反対する中自分の意志を貫き失敗することもあるかもしれませんが、その経験は貴重な財産です。
また、入学、就職など大きな環境の変化があっても「どうすれば乗り越えられるかな?」と自分の力で解決策を出すことができます。
1日中考える力を伸ばすための会話をする必要はないので、朝などの忙しい時間は避け、余裕があるときにはぜひ思考力を伸ばす会話を交わしたいですね。
お皿洗いながら、洗濯しながら聞ける動画バージョンはこちら🎵🎵
考える力は学習意欲にも繋がっていく
考える力を伸ばす鍵は、会話の中だけにあるのではありませんよ😁
考える力を伸ばすステップ1「自ら疑問を持つ」ことについてですが、子どもの疑問は毎日の生活の中にたくさんちりばめられています。
「どんな手触りかな?」「ここを歩くとどうなるかな?」「食べかけのクッキーは何に見えるかな?」といった子ども特有の疑問は、考える力を伸ばす大事な種です🌱
触ってほしくないもの、歩くと危険な場所もあるので、安全な範囲で疑問に応えてあげたいですね。
子どもの疑問の前には、さらに2つのステップが隠れています。
好奇心(あの石はなんだろう?)
↓
観察(上を歩けそうだな)
↓
疑問(歩いたらどんな気分になるかな?)
↓
想像(ハラハラした気持ちが味わえるかもしれない!)
↓
さらなる思考(1回だけなら歩かせてもらえるかな?)
・
・
・
本来子どものなかで常に回っているこのサイクルは、学習意欲につながっていきます✨✨
誰かに教えられる「勉強」という行為より、自ら行う「学習」の方がより定着し、自分の力になっていきますよね🌼
考える力のある子は自然と学習意欲も育ち、いずれ自分の好きなことを見つけ、取り組み、決断し、必要なら周りの助けを借りながら人生を歩んでいくことができるのです⤴⤴
お皿洗いながら、洗濯しながら聞ける動画バージョンはこちら🎵🎵
考える力は自然には育たない
子どもは好奇心のかたまり!
そのパワーは本当に素晴らしいもので、エネルギーにあふれており、無限の可能性を持っています。
しかし、私たち大人は良かれと思って先回りした発言をしがちです💦💦
しかも、恐ろしいことに、その先回りがどれだけ子どもの好奇心を削ぎ考える力を奪っているかを知らないままに😖
子どものためと願いながら子どもの能力をすり減らしては本末転倒です。
完璧にこなさなくても大丈夫なので、子どもに考える「隙」を与えられるような会話を心掛けたいですね✨✨
お皿洗いながら、洗濯しながら聞ける動画バージョンはこちら↓から🎵🎵
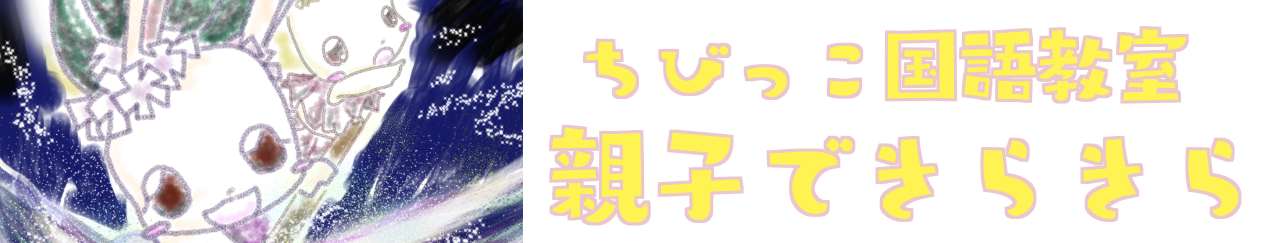
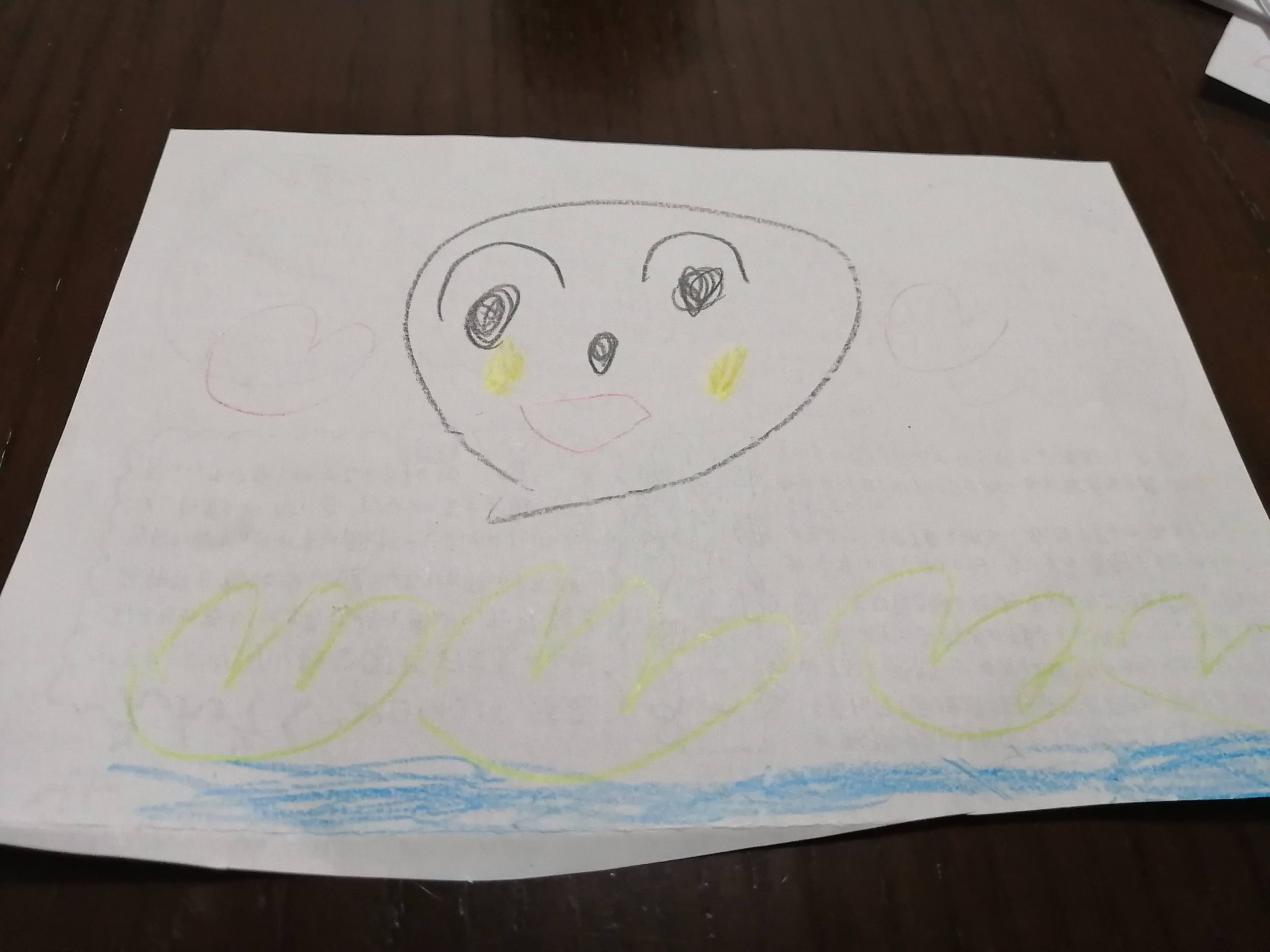


コメント